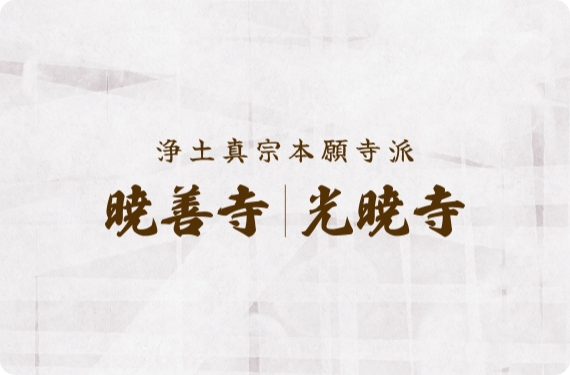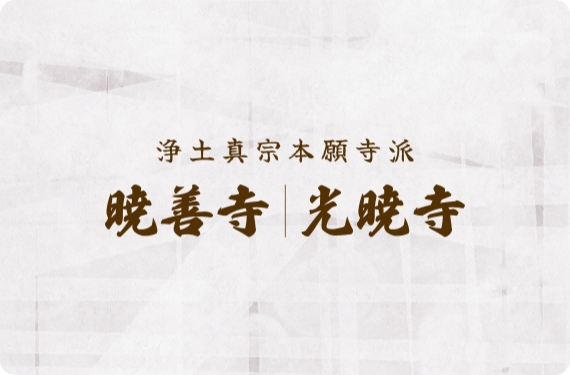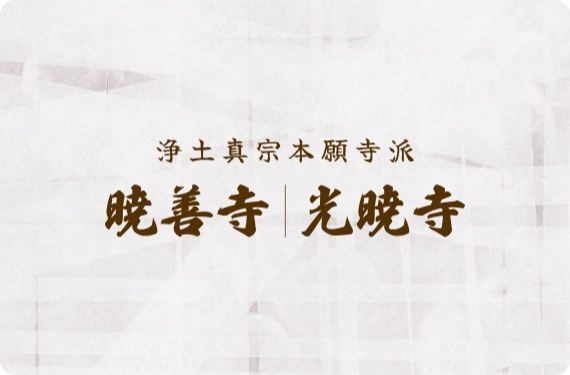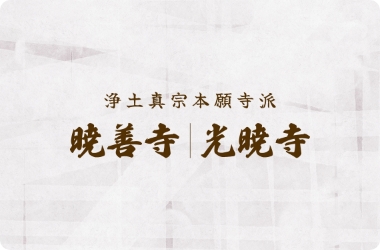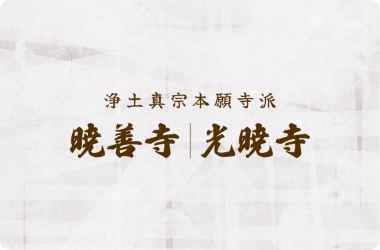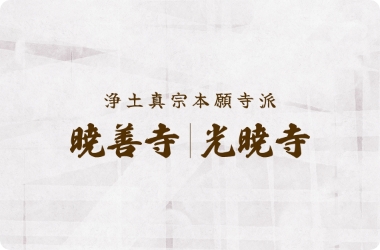当寺の歴史
当寺の歴史について
暁善寺・光暁寺は、ともに明治・大正期の開拓時代に、地域の人々と歩みながら法灯を受け継いできた寺院です。暁善寺は1899年、厚岸尾幌の地に初代佐藤暁善師が開創し、光暁寺は1920年、上尾幌にてその志を引き継いで設立されました。信仰と教育を通じて地域に根ざし、幾多の困難を乗り越えてきた歴史があります。現在も「心の依り処」として、地域とともに生きる仏教の実践を続けております。共に感じ、共に育む~
『仏に願われたいのち』をともに生きる

きょうぜんじ
浄土真宗本願寺派 慈光山暁善寺
1899年(明治32年)、初代佐藤暁善師が厚岸・教雲寺ご住職のすすめで尾幌説教所を開創されました。
1899年4月26日、釧路郡大字仙鳳趾村字敏内(ピンナイ)の地に、富山県西砺波郡から胆振国鵡川郡を経た28戸が上陸。大分県中津郡出身者の開設する農場に入植されていました。実にお念仏のご縁篤き地に法灯が、灯ります。
暁善師自身が水害に追われ、越中のご門徒さんいずれもが富山、鵡川で再度の洪水を経ています。海岸線に近く、広大な原野に恵まれた尾幌殖民区画地に<再生の礎>を定めました。
暁善師は1900年6月20日、寺子屋教育が開始され、のちの厚岸町立尾幌小学校の前身となります。
1917年(大正6年)12月、鉄道が開業されます。開村地域の北側に尾幌駅が設置され、また1933年(昭和8年)3月29日に説教所が焼失する<めぐりあわせ>を経て、現在地に寺基を移しました。1950年に暁善寺の寺号を公称する運びです。
1980年(昭和55年)本堂改築慶讃法要、第二代佐藤義昭住職が発願し、1989年(平成元年)五月六日、七日に開教90周年法要が勤修されます。
泥炭湿地に尾幌川氾濫が重なる悪条件のもと、開墾にいそしんでこられた皆さんに今も心寄せつつ、地域の生涯教育、住民活動に向きあわせていただいています。
□(開基)釋暁善師(~1915年)、釋暁信師(~1932年)、(二代)釋義昭師(~1997年)、(現世)釋暁慎師。
所在地
〒088-0871
北海道厚岸郡厚岸町尾幌455番地
暁善寺の歴史
- 明治32年 4月26日
- 敏内浜に上陸し、二十八戸が入植
- 明治32年 9月1日
- 真宗本願寺派尾幌説教所開設
- 明治33年 3月
- 尾幌婦人積善講結成(のちのあかつき仏教婦人会)
- 明治33年 6月20日
- 寺子屋教育開始(尾幌小学校開校記念日)
-
明治42年 6月1日
- 校舎が完成し、尾幌小学校となる
- 明治44年 11月22日
- 初代坊守 佐藤 貴之枝 が新潟県より入寺
- 大正14年3月27日
- 開基住職 佐藤 暁善 法師が往生(行年五十歳)
- 昭和7年 9月19日
- 暁信 法師(暁善師長男)が往生(行年二十歳)
- 昭和8年 3月29日
- 尾幌説教所焼失
- 昭和9年 5月5日
-
本堂落成慶讃法要
第二世住職 佐藤 義昭 得度受式
尾幌仏教婦人会 本願寺仏婦連合本部認定
- 昭和10年
- 仏教青年会 結成
- 昭和13年
- 日曜学校 開設
- 昭和15年
- 第二世住職 佐藤 義昭 教師補任
- 昭和17年
- 宗教団体法により尾幌教会と改称
- 昭和18年
- 第二世住職 佐藤 義昭 本願寺布教使拝叙
- 昭和20年
- 尾幌小学校空襲焼失 臨時教室貸与
- 昭和21年
- 第二世坊守 佐藤 美代 が新潟県より入寺
- 昭和24年
-
開基五十周年法要 開基住職二十五回忌
御木仏本尊御入仏
- 昭和25年 5月25日
-
宗教法人令により慈光山暁善寺と公称
第二世住職 佐藤 義昭法師 住職拝命
- 昭和36年
- あかつき仏教婦人会本願寺仏婦総連盟登録
- 昭和37年
- 暁善寺護持会結成
- 昭和38年 3月22日
- 開基坊守 佐藤 貴之枝 が往生(行年七十三歳)
- 昭和41年
- 納骨堂竣工、御木仏御入仏
- 昭和44年
- 開基七十周年記念法要
- 昭和50年 2月21日
- 第三世住職 佐藤 暁慎 得度受式
- 昭和52年 11月30日
- 第三世住職 佐藤 暁慎 教師補任
- 昭和55年
-
第三世坊守 佐藤 佳子 が静岡県より入寺
再建本堂落成慶讃法要
- 昭和58年
- 暁善寺門信徒会結成
- 昭和60年
-
御宮殿備付御入仏慶讃法要(開基坊守二十三回忌記念)
第三世住職 佐藤 暁慎 本願寺派学階 助教拝受
- 昭和61年
- 御開山厨子備付御影開軸慶讃法要
- 昭和62年
- 第三世住職 佐藤 暁慎 本願寺布教使拝叙
- 平成元年 5月6日・7日
- 開基九十周年記念法要
- 平成9年 4月11日
- 第二世住職 佐藤 義昭 法師が往生(行年八十一歳)
- 平成10年 10月20日
- 第三世住職継職法要
- 平成13年 1月14日
- 第二世坊守 佐藤 美代 が往生(行年八十六歳)
- 平成16年 2月
- 衆徒 佐藤 明功 得度受式
- 平成20年 8月
- 衆徒 佐藤 明功 教師補任
- 平成25年
-
ビハーラ講座をはじめる
供養塔・合同墓開眼法要
- 平成30年 2月
- 衆徒 佐藤 智暁 得度受式
- 令和2年 3月
- 衆徒 佐藤 智暁 教師補任
- 令和5年 5月
- 衆徒 佐藤 智暁 本願寺布教使拝叙
- 令和5年 10月23日
-
開基住職百回忌・第二世住職二十七回忌
・第二世坊守二十三回忌法要
地域とともに歩むお寺
~あなたの生きるを支える心の依り処~

こうきょうじ
浄土真宗本願寺派 顕真山光暁寺
1920年(大正9年)、浄土真宗本願寺派尾幌説教所の主管者佐藤暁善師が主管者を務め、上尾幌説教所を開創されます。
上尾幌は釧路・厚岸両郡の郡界に源流部を有する尾幌川の上流域で、原始林・石炭資源の宝庫でありました。
1917年(大正6年)12月北海道官設鉄道・根室本線上尾幌駅開業に先立ち国有地72区画が払いさげられました。
官行斫伐(かんこうしゃくばつ 国有林伐採事業)、民営の林業・製材業、石炭採取事業者及び勤務者が定住。木材・石炭を運送する産業用馬、運送業などサービス業が各地から集まったのです。
1940、41年(昭和15、16年)にむけ戦時石炭増産と重なり5000人居住の大集落。移住一世ばかりの地ながら、近隣集落とは距離がありました。そこで尾幌川中流域の尾幌説教所主管者に託され、上流域に支院開創の運びとなりました。
厚岸町内で新潟県出自の漁業家さんのご支援を忝くし、富山県出身のご門徒さんが別家創設の動き。安芸ご門徒の影響をつよく受けた周防国(すおうのくに)吉川家(きつかわけ)家臣のお方、太田屯田兵ご子孫にも支えられました。
戦後、さらに食糧緊急確保の農業開拓に大陸、樺太・千島の引揚者で、一時は2500人居住の時もありました。浄土真宗本願寺派、真宗大谷派のご門徒はもとより、曹洞宗、真言宗、日蓮宗のお檀家さんも、お力添えくださいました。
地域の教化機関として日曜学校、仏教青年会、仏教婦人会に宗派を超え、足をお運びくださり「講=聞法のたしなみ」は実に高く、戦後、上尾幌教会親和会発足の折には地域で9割超のお方が会員になってくださいました。
篤信の思い尊く、1978年(昭和53年) 本堂改築落成慶讃法要、あわせて光暁寺と寺号公称の運びとなりました。
□(開基)釋暁善師(~1915年)、釋暁信師(~1932年)、(二代)釋義昭師(~1998年)、(現世)釋暁慎師。
所在地
〒088-0771
北海道厚岸郡厚岸町上尾幌123番地